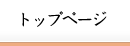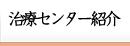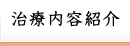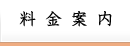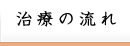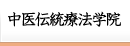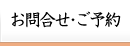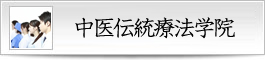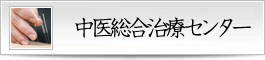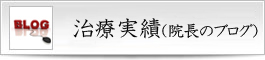尿閉症の施術例 症例紹介 鍼+気功推拿治療
症例 40代 女性 尿閉症と診断されてから1年半 2013年10日17日に来院
6年ぐらい前から尿が時々でにくくなるが、思い当たる原因はなく、腎・膀胱の超音波や採血検査にも異常が見られなかったため、特に治療を受けてはこなかった。
2012年の11月ごろに、腹部にガスが溜まっていて、内科に受診し、胃腸薬(モサプリド クエン酸塩とメトクロプラミド)を4日間分もらい、これを飲み終わってからカゼぎみになり、感冒薬を飲んだ。翌朝になってから尿閉となり、冷汗、腹脹がひどく、救急車で病院の外来に行き、導尿してもらい、500㏄ほど尿を出した。翌日に泌尿科に行ったが診断は「原因不明」。400㏄ほど導尿し、その翌日なんとか排尿したが、尿の出方は点滴のようにわずかで、ずっと残尿感がある。2012年11月中旬に総合病院にて膀胱造影してもらい、その後、脳神経科に受診し、問題なしという結果だった。膀胱収縮させる薬(ジスチグミン臭化物)を処方され2013年2月までには残尿感が軽減した。
2013年の7月に、腹部にガスがたくさんたまるようになった。昼になると腹部の張りがひどく、特に食後に大量のガスが発生し、お腹がパンパンになるため、別の消化器内科に診療し、消化管運動調整薬(トリメブチンマレイン酸塩)、乳酸菌製剤(ラクトミン)、半夏瀉心湯を処方されたが、これらを飲んでもガスが減らず、朝に便もでない。9月末に緩下剤を朝晩に2回飲むようにしたら、かえって朝の便通やおならも止まってしまい、こういった状況が2週間続いた。
10月13日に旅行先で朝10時に最終尿となり、膀胱に尿がいっぱいでもトイレにいっても排尿できず、無尿のまま、腹部のはりもひどくなっていった。翌朝(14日)の5時に現地の病院を受診し1600㏄を導尿で出した。その後、旅行から戻ったものの、尿の出方は点滴のようだった。17日の朝、排尿姿勢を変えたり力を入れたりしてもポツリポツリとしか尿が出ず、昼ごろ試しに水を飲んでみたが、尿意はおこるが、トイレへ行っても排尿せず、同日、知人の紹介で来院。
現症状:
*尿閉(ほとんど出ない)、腹脹(腹部にガスが溜まっている)、
望 診:
*下腹部は隆起
*舌体胖大、苔厚膩
触 診:
・膀胱底部が臍下の2指半まで上がってきた。
・肝脈弦滑、両尺部に沈遅
辨 証:尿閉症(中医学診断名:癃閉)
発症機理:脾腎両虚、気化不能
治療方針:温補脾腎、化気行水
治療方法:鍼+気功推拿(週に3回)
治療結果:
・初回治療の当日(10月17日)、自宅に戻ってから19時・19時30分・21時・22時と4回排尿あり。排尿のたびにおならがたくさん出るようになった。
・治療の翌日朝の6時・10時・11時・14時・16時30分に5回排尿あり。ベッドから起き上がる際の体の動きもスムーズになり、背中、腰部の痛みも減軽した。
・引き続き18、19日の2回の治療後には食事の後でもガスが腹部にたまらなくなった。
・4回目(10月23日)の来院時には6時・7時・8時10分・13時・14時・18時に排尿。ご本人様曰く、気持ちよく排尿されたとのこと。「排尿の感覚が元通りに戻ってきた。排尿の感覚がこれだ」。
・・・・
現在は2~3週間に1回、健康維持のために来院している。
治療感想:
尿閉とは、膀胱内に尿が多量に貯留し、尿意があるにもかかわらず排尿できない状態をいいます。原因不明のため、治療が困難な場合もあると言われています。この場合、導尿が不可欠な治療法となりますが、導尿を繰りかえすと膀胱炎を引き起こす可能性もあります。
中医学では尿閉症のことを癃閉と称します。発病は脾腎肺肝の働きと関係が深く、この患者さんの発病原因としては脾腎肝の働きの異常と判断しました。気功推拿と鍼を用いて脾腎肝の働きを調節することで、2週間の短い期間で体調を整えることができました。
今回のケースのように西洋医学の診断結果では『原因不明』となる種々の病気も、中医学の診断では症状・舌質・舌苔・脈から総合的に診断を行いますので、発病原因や体内の異常変化が中医学の理論的に推測可能です。中医学の考え方では、『症状』は体内の異常変化の『結果』です。結果があれば、『原因』も必ずあるのです。